土地や家の相続税が払えない時の対処法|生前贈与や土地活用で税負担を減らす方法も解説
2025.03.20
2025.04.09
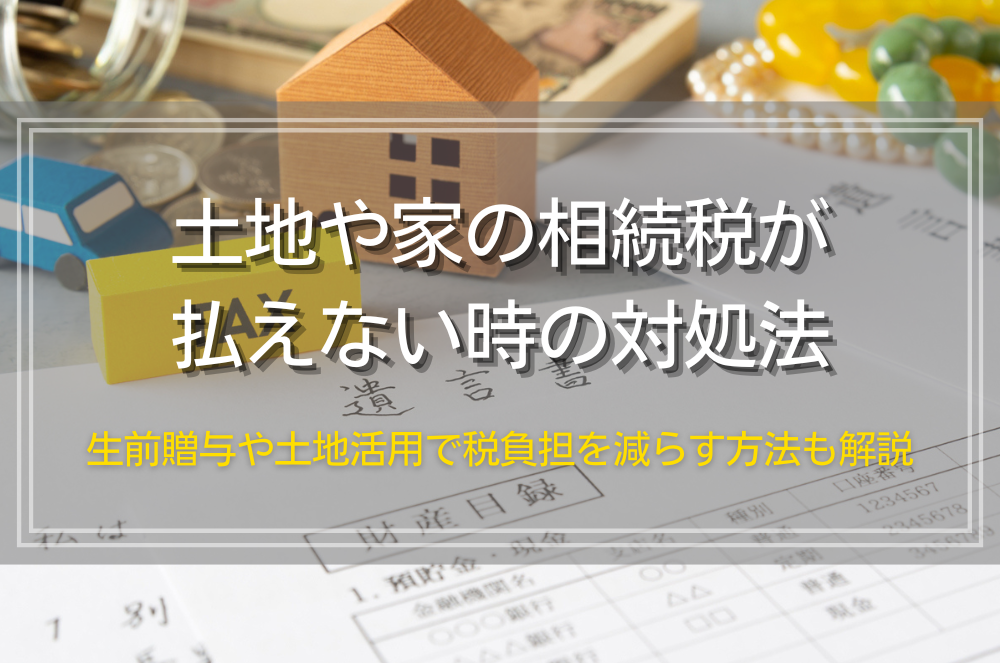
このコラムでは、土地や家を相続した時の相続税が払えない時の対処法について解説します。
延納(分割払い)・物納制度や、財産の売却、ローンを借りるなど、それぞれの方法のメリット・デメリットを分かりやすくまとめています。
また、生前贈与や土地活用など、相続発生前にできる税負担を抑える方法についても紹介。これから土地や家を相続予定の方は参考にしてください。
コラムのポイント
- 相続税が高額になりそうな時や、不動産のように換金しづらい財産の割合が多い場合は、事前に対応策を考えておくことが重要です。
- 相続税の一括払いが難しい場合は、延納・物納制度を活用する、相続不動産を売却して納税資金に充てる、相続税関連資金に使えるローンを借りるなどの方法を検討しましょう。
- 活用していない土地や空き家を相続する予定があるなら、アパートや駐車場経営などで活用することで相続税対策になる場合もあります。
Contents
相続税が発生するタイミングと納付期限
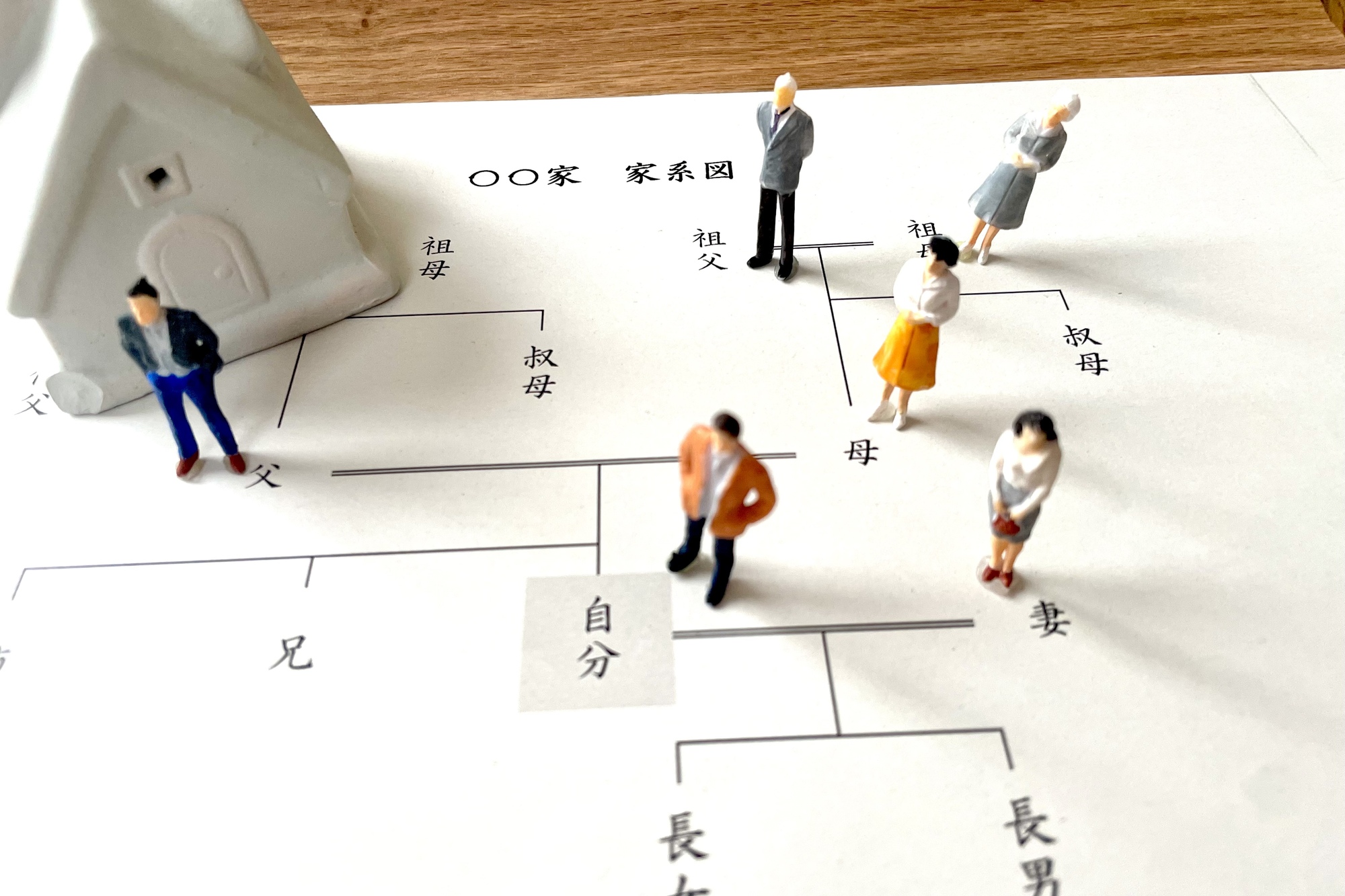
土地や家などの不動産、現預金などの財産を引き継いだ際は、金額・評価額に応じた相続税を納付しなければなりません。
相続税の納付期限は、相続が発生してから10か月以内で、原則として現金で一括納付する必要があります。
ただし、相続税には基礎控除などの非課税枠があるため、相続財産が一定の金額以下なら相続税を支払う必要はありません。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
上記の基礎控除額が大きいことに加え、不動産の相続では「小規模宅地等の特例」などさまざまな軽減措置もあるため、基礎控除と特例利用で相続税がゼロになるケースも多いでしょう。
国税庁の統計によると、令和5年分の相続税課税割合は9.9%で、相続税の申告をした人のうち、相続税が発生した人は約1割程度となっています。
相続税が払えない代表的なケース

相続税が払えない状況としては以下のようなケースがあります。
すぐに換金できない相続財産が多い
相続税は、原則として現金で一括納付する必要があります。
相続した財産のうち、不動産などすぐに換金が難しい財産が多い場合、納税資金が用意できないケースがあります。
- すぐに現金化しやすい財産…現金・預貯金、株式(上場株式・投資信託等)、債権、投資信託、保険などの金融資産
- すぐに現金化しづらい財産…不動産(土地や建物)などの実物資産
ただし実物財産でも、仲介による売却ではなく買取を利用すれば比較的短期間で現金化できる場合もあります。
〈関連コラム〉
不動産売却は仲介と買取どっちが良い?メリット・デメリットと向いているケース、「買取保証付き仲介」についても解説
空き家買取の基礎知識|メリット・デメリットや不動産会社選びのポイントを解説
不動産買取の注意点!デメリットや買取金額が安くなる理由を解説
相続不動産が売却できない
相続不動産を売却した代金で相続税を支払おうと考えていた場合、相続から10か月以内に売却し、確定申告を済ませる必要があります。
買い手が見つからずなかなか売却できない場合、相続税の納期限に間に合わなくなる可能性があります。
〈関連コラム〉
相続した不動産を売却する流れ|税金や必要書類、相続人同士での分割方法も解説
相続した空き家の売却でかかる税金は?計算方法や「空き家特例」を活用した節税方法も解説
実家が空き家になったらどうする?相続手続きの流れと管理・活用・売却時のポイントを解説
被相続人の口座から預貯金を引き出せない
相続税を被相続人の預貯金で支払おうと考えている場合、被相続人の口座から引き出しができないと支払いが難しくなります。
通常、金融機関は口座名義人が亡くなったことを確認すると、口座を凍結します。口座の凍結を解除するためには、遺産分割協議を成立させる、遺言で指定された預金口座の相続人が手続きするなどの方法があります。
例えば、遺産分割協議でトラブルになった場合、全員の同意が得られるまで被相続人の預金を引き出せなくなってしまいます。
ただし、2019年7月1日の民法改正で銀行の「預貯金の仮払い制度」がスタートし、遺産分割前でも一定額までは相続預金を払い戻しできるようになっています。
仮払い制度で払い戻しができる額は「相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分」です。
相続税を払えない時の対処法

前章で述べたような状況によって、相続税の支払いが難しい場合の対処法について解説します。
- ①延納制度を利用して分割払いする
- ②不動産で物納する
- ③不動産を売って納税資金に充てる
- ④金融機関から融資を受けて納税する
- ⑤相続放棄する
それぞれの対処法について、1つずつ詳しく解説していきますね。
延納制度を利用して分割払いする
相続税の一括納付が難しい場合、要件を満たせば最大20年間にわたって分割払いができる「延納制度」を活用する方法があります。
相続税が高額な場合、分割納付することで不動産を手放さずに済むのがメリットです。
ただし、延納期間中は利子税がかかるため、最終的な納税額が増えてしまうデメリットがあります。
相続税の延納を申請するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 相続税額が10万円を超えている
- 金銭での納付が困難な理由があり、延納する金額が納付困難な金額の範囲内である
- 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供する※延納税額が100万円以下かつ、延納期間が3年以下の場合は担保不要
- 相続税の納期限等までに延納申請書と必要書類を提出する
金銭以外の相続財産で納める(物納)
上記の延納制度を利用しても相続税の納付が難しい場合、要件を満たせば「相続財産による納付(物納)」ができます。
物納制度が利用できる要件は以下の通りです。
- 延納制度を利用しても相続税の納付が難しい理由があり、物納する金額が納付困難な金額の範囲内である
- 国税庁が定めた物納申請できる財産がある(不動産や国債、株式、動産など)
- 相続税の納期限等までに物納申請書と必要書類を提出する
なお、不動産についてはローン返済中(抵当権が設定されている)や境界が不明瞭な物件などは物納申請できないなど細かい条件があるため、事前に国税庁のホームページで要件を満たしているか確認しましょう。
相続財産を売却して納税資金に充てる
相続財産を売却して現金に換えて、相続税の納税資金に充てる方法です。
相続人が複数いる場合、土地や家などの相続不動産を売却するためには、相続人へ所有権移転登記を済ませなければなりません。相続人が複数いる場合は、早めに遺産分割協議を開始し、売却する遺産について全員の意見をまとめることが重要になります。
ただし、土地や家などの不動産は期限までに売却できなかったり、思ったような金額で売れなかったりする可能性もあるので注意が必要です。
また、相続不動産を売って得た利益に応じた譲渡所得税の支払いが必要になる場合もあります。
ただし、相続開始から3年以内の売却なら「相続税の取得費加算の特例」を適用して譲渡所得税を節税できる可能性もあります。
〈関連コラム〉
相続した土地を3年以内に売却すると節税できる?「相続税の取得費加算」「空き家特例」の適用要件や手続き方法、注意点を解説
金融機関から融資を受ける
金融機関が提供している、相続関連資金に利用できるローンを組み融資を受けて、納税資金に充てる方法です。
ローンの金利が相続税の延納にかかる利子税よりも低ければ、分割払いによる負担増を抑えられる可能性もあります。
ただし、融資を受けるには審査に通らなければならない他、担保や保証人が必要になる場合もあります。金融機関によって融資条件や金利も異なりますので、必ず延納より負担が少なくなるとは限らない点に注意が必要です。
相続放棄する
相続放棄とは、被相続人の資産や負債など、財産全てに対する権利や義務を放棄することを指します。
相続開始を知ってから3か月以内に手続きする必要があります。
相続放棄をした人は「はじめから相続人でなかった」ものとみなされるため、相続税の支払い義務がなくなり、借金などのマイナスの財産を相続しなくて済むメリットがあります。
ただし、預貯金や不動産などのプラスの財産の相続権利もなくなるため、相続税の負担を無くすためだけに相続放棄をするべきかどうかは慎重に判断する必要があります。
〈関連コラム〉
空き家を相続放棄するメリット・デメリット|ほかの対処法も解説
相続税を払わないとどうなる?

相続税を期限までに納付しなかった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生します。
無申告加算税は期限までに納税しなかった時にかかる税金で、税率は申告時の状況や税額によって変わります。
- 税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合…納付する税金×5%
- 税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合…
納付する税金が50万円までの部分は10%、50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25% - 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合…納付する税金×15%
納付する税金が50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%
(参考)国税庁ホームページ|No.2024 確定申告を忘れたとき
延滞税は、各種税金の納付期限を過ぎた場合にかかる税金です。
- 納付期限翌日から2か月以内…納付する税金×7.3%/年
- 納付期限翌日から2か月以降…納付する税金×14.6%/年
上記のように、延滞した期間が長いほど無申告加算税や延滞税も高くなります。
さらに、相続税を滞納し続けると、国税庁から財産を差し押さえられたり、連帯納付義務で他の相続人に督促が行く可能性もあるため、期限内の納税が難しい場合は、早めに対処法を検討しましょう。
〈関連コラム〉
相続した土地や家を売った時の確定申告|自分でする流れや必要書類、申告不要なケースを解説
相続予定の土地や家の税負担を抑えるための対策方法

これから土地や家を相続する予定の方へ向けて、相続が発生し納税時に慌てないためにできる対策を紹介します。
相続時精算課税制度で不動産の生前贈与を受ける
相続時精算課税制度とは、生前贈与で土地などの財産を取得すると、2,500万円分まで贈与税がかからない代わりに、相続時に生前贈与分を相続財産にプラスした上で相続税が課税されるという制度です。
本来は贈与された時点で支払う必要がある贈与税を、相続発生時に相続税で払うというイメージです。
相続時精算課税制度で贈与した場合、贈与財産は相続財産に加算しますが、不動産の評価額は贈与時の時価になります。
将来的に土地の価値が上がることが見込まれる場合には、相続時精算課税制度を選択して贈与を受けることで相続時の税額を抑えられる可能性があります。
また、税金対策以外でも、以下のような場合は生前贈与を検討しても良いでしょう。
- 相続トラブルを避けたい
- アパートなどの収益物件が建っている
- 相続まで待たずに土地を早く活用したい
- 相続人以外を含む特定の人に土地を引き継ぎたい
〈関連コラム〉
土地は生前贈与と相続のどちらが得?メリット・デメリットや税金・手続きにかかるコストシミュレーションを紹介
賃貸経営や駐車場などに活用する
相続する不動産が活用していない土地や空き家の場合、アパートを建築したり駐車場などに転用したりすることで相続税対策になる場合もあります。
例えば、所有する更地にアパートを建てたり、空き家をリノベーションして賃貸に出したりする場合、被相続人が工事費を負担すれば相続財産を圧縮でき、貸家建付地の評価減の特例によって相続時の土地の評価額を下げられます。
〈関連コラム〉
貸家建付地による相続税対策をわかりやすく解説|相続税評価額の計算方法もチェック
相続空き地の活用方法14選|ビジネスアイデアや自治体との連携など解説
まとめ
相続税が高額になりそうな時や、不動産のように換金しづらい財産の割合が多い場合は、事前に対応策を考えておくことが重要です。
相続税の一括払いが難しい場合は、延納・物納制度を活用する、相続不動産を売却して納税資金に充てる、相続税関連資金に使えるローンを借りるなどの方法を検討しましょう。
また、活用していない土地や空き家を相続する予定があるなら、アパートや駐車場経営などで活用することで相続税対策になる場合もあります。
親の土地や家を引き継ぐ予定がある場合は、相続発生前に生前贈与や活用の計画を立てておくことで、税金や手続きの負担を抑えながら、スムーズに土地を引き継いで有効活用できるでしょう。
東京・千葉エリアで土地の相続についてお悩みの際は、未来の財託へご相談ください。
贈与税・相続税対策のノウハウが豊富なスタッフが、お客様の状況をお伺いし適切なプランをご提案いたします。


 0120-210-341
0120-210-341
