相続した土地や家を売った時の確定申告|自分でする流れや必要書類、申告不要なケースを解説
2025.02.05
2025.02.19
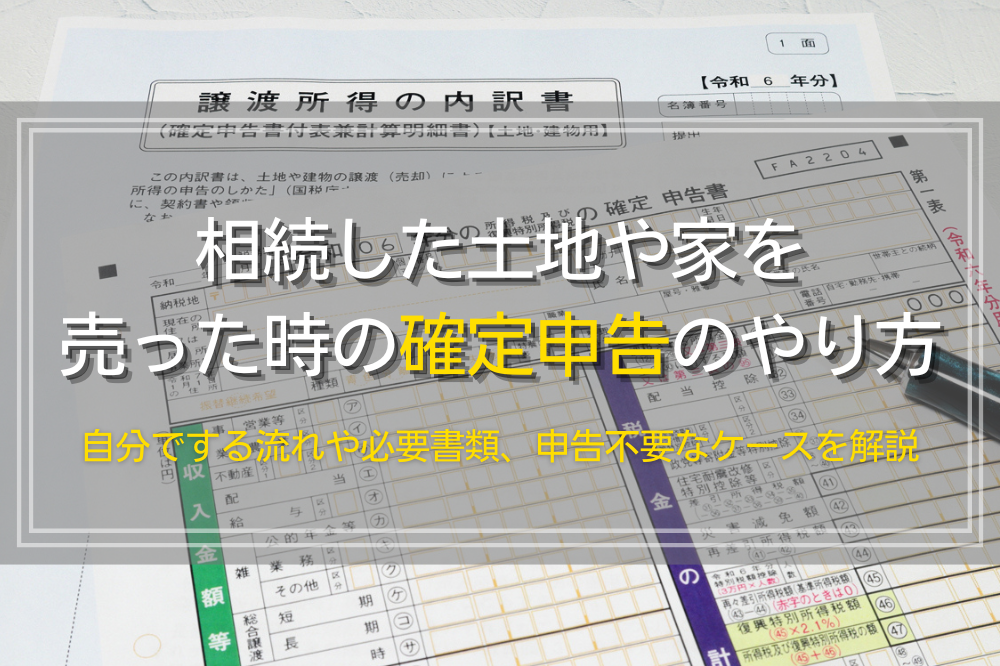
相続した土地や家を売って利益が出た場合は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をし、課税所得に応じた税金(譲渡所得税)を納める必要があります。
申告時には被相続人の時代からのものも含めてさまざまな書類や情報が必要になり、期限内に手続きを済ませなければならないため、手間や時間がかかります。
このコラムでは、相続不動産売却時の確定申告を自分でする際の手続きの流れや必要書類、e-Taxの利用方法、特別控除などの節税につながる制度を紹介します。
コラムのポイント
- 相続した土地や家を売って利益が出た場合は、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をし、課税所得に応じた税金(譲渡所得税)を納める必要があります。
- 譲渡所得税は、要件を満たしていれば、課税所得から最大3000万円を控除できる「空き家特例」や、相続税の一部を売却物件の取得費に加算できる特例などを適用して節税することもできます。
- 不動産の相続を控えている場合は、信頼できる不動産会社へ、適用できる特例や売却方法について早めに相談することをおすすめします。
相続不動産を売って利益が出たら確定申告、納税が必要

相続した土地や建物を売却し、以下の計算式によって譲渡所得(利益)が出た場合は、譲渡所得に対して所得税および住民税が課税されるため、原則として確定申告が必要です。
譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用 ) = 譲渡所得(利益)
| 譲渡価額 | 不動産を売却した代金
(売却時の固定資産税・都市計画税の精算金も含まれる) |
| 取得費 | 不動産を購入する際にかかった金額の合計
|
| 譲渡費用 | 不動産を売却するために直接かかった費用
※修繕費や固定資産税などの維持管理費用や、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。 |
(参考)国税庁ホームページ|令和6年分確定申告特集|不動産等を売却した方へ
なお、相続した土地建物が先祖伝来のものであったり、購入時期が古かったりして取得費が分からない場合には、売却金額の5%相当額を取得費とする特例があります。
(参考)国税庁ホームページ|令和6年分確定申告書作成コーナー|取得費が分からないとき(概算取得費の特例)
実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様に、売却金額の5%相当額を取得費にできます。
確定申告が不要なケース
譲渡所得金額がゼロかマイナス
売却価格から取得費や譲渡費用を引いた結果がゼロやマイナスとなり利益が出なかった場合は、課税対象となる所得が存在しないため、所得税はかからず確定申告も不要になります。
ただし、損失分を他の不動産所得と相殺できる「譲渡損失の繰越控除」を利用する場合は、確定申告が必要になります。
譲渡損失の繰越控除については後の章で詳しく解説します。
譲渡所得と他の所得の合計が20万円以下の場合
相続不動産を売却して譲渡所得が出ても、他の所得と合わせて20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。
※ただし、所得が20万円以下の場合でも住民税の申告は必要になります。
給与所得者(会社員など)で、不動産売却による譲渡所得が20万円以下の場合、下記2つにあてはまっていれば確定申告は不要です。
- 給与をもらっている勤務先が1か所
- 勤務先で年末調整を受けた
相続した不動産売却後の確定申告を自分でする流れ
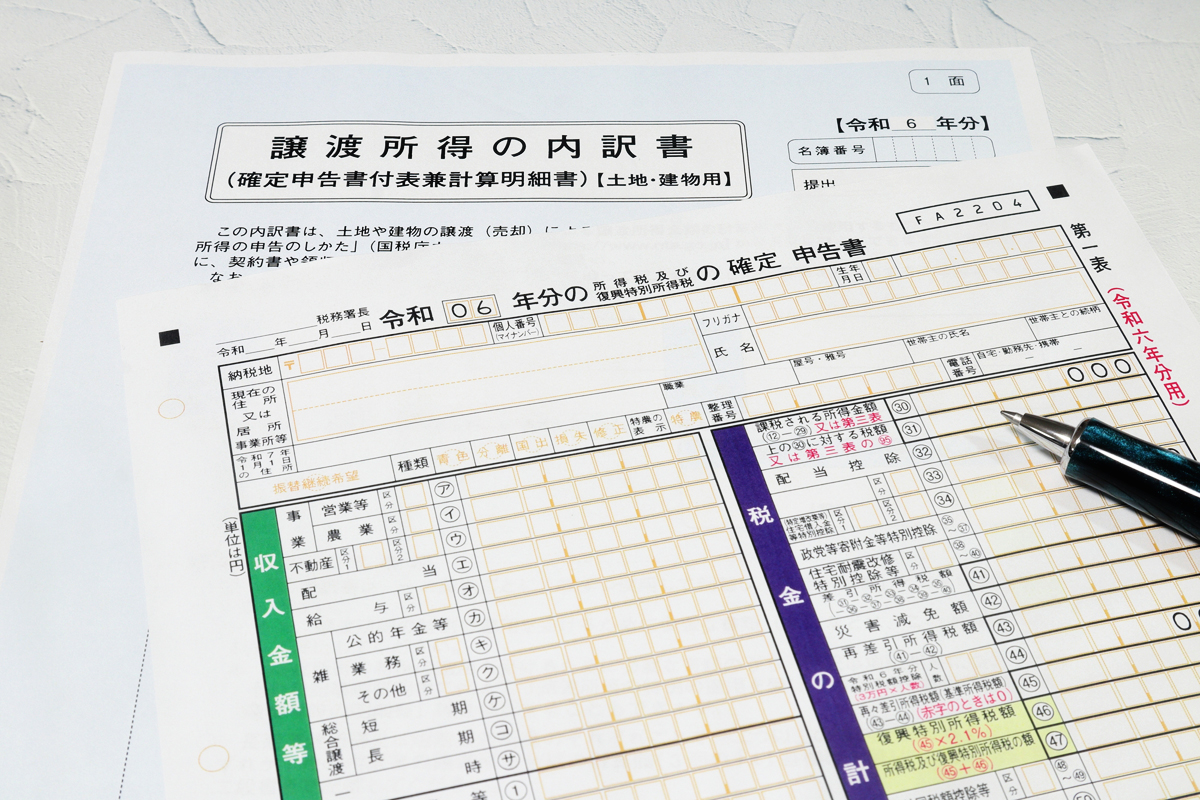
相続した土地や家を売って、譲渡所得金額(利益)があった場合の確定申告のやり方をまとめます。
①必要書類の準備
相続した土地や家を売却した場合の確定申告に必要な書類は以下の通りです。
| 必要書類 | 概要や書類の入手方法 |
|---|---|
| 確定申告書第一表、第二表および第三表(分離課税用) |
税務署や申告会場で入手、国税庁のホームページから印刷 |
| 譲渡所得の内訳書【土地・建物用】 |
税務署や申告会場で入手、国税庁のホームページから印刷 |
| 不動産の売却価格が分かる書類 |
|
| 譲渡費用関連の証明書類の写し |
|
| 不動産購入時の価格が分かる書類 |
|
| 取得費用関連の証明書類の写し |
|
| 不動産の売却価格が分かる書類 |
|
| 本人確認書類の写し |
|
| 源泉徴収票 |
|
この他、後述する相続空き家の3000万円特例控除などを利用する場合は、家屋・敷地の登記事項証明書や、「被相続人居住用家屋等確認書」などが別途必要になります。
②適用できる不動産売却時の特例を調べる
特例が適用できれば譲渡所得税を節税でき、税額がゼロになる場合もあります。
相続不動産を売却する時に使える主な特例を紹介します。
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別特例
要件を満たして、相続した空き家を3年以内に売却すると譲渡所得の金額から3,000万円※まで控除される特例です。「空き家特例」とも呼ばれ、適用できれば大きな節税効果を得られます。
※対象の不動産を相続により取得した相続人の数が3人以上の場合は控除額上限2,000万円までとなります。
(参考)国税庁ホームページ|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
例えば譲渡所得が1,000万円の場合、所有期間15年以上の場合200万円強の税負担が発生しますが、空き家特例が適用できれば税金がゼロになります。
特例を適用するためには空き家を解体するか、新耐震基準を満たした上で売却する必要があります。
特例が使えるかどうかは、以下のチェックシートなどで確認しておきましょう。
(参考)国税庁ホームページ|相続した空き家を売却した場合の特例チェックシート(令和6年分用)
〈関連コラム〉
空き家特例で上手に節税!3,000万円控除の要件をわかりやすく解説
相続した空き家の売却でかかる税金は?計算方法や「空き家特例」を活用した節税方法も解説
マイホームを売った時の3,000万円特別控除
マイホーム(居住用財産)を売った時は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
被相続人と一緒に住んでいた家を、相続した後に売却した場合などで利用できる可能性があります。
(参考)国税庁ホームページ|No.3302 マイホームを売ったときの特例
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、特例の条件を満たしているか確認しながら申告書を作成できます。
相続税の取得費加算の特例
相続した不動産(土地や建物)を一定期間内(相続開始から3年10か月以内)に売却した場合、相続税額の一部を売却した不動産の取得費に加算できる特例です。
特例を適用して売却した不動産の取得費が高くなると、課税対象の譲渡所得を減らせるため、結果的に譲渡所得税の節税になります。
相続税が高い人ほど、また相続財産価額の中で売却する不動産の割合が多いケースほど、譲渡所得税が節税できる額が大きくなるため、「相続する財産が土地のみで相続税額が高い」という方に恩恵が大きい特例となります。
〈関連コラム〉
相続した土地を3年以内に売却すると節税できる?「相続税の取得費加算」「空き家特例」の適用要件や手続き方法、注意点を解説
③納税額を計算する
譲渡所得税の納税額は、以下の計算式で求めます。
不動産の売却価格-(不動産の取得費+譲渡費用)-特別控除=課税される譲渡所得
↓
課税される譲渡所得×税率=納税額
譲渡所得の税率は、空き家を所有していた期間によって以下のように変わります。
| 譲渡所得の種類 | 譲渡所得税率 | 住民税率 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得
(譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える) |
15% | 5% |
| 短期譲渡所得
(譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下) |
30% | 9% |
※2037(令和19)年までは、「復興特別所得税」として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付する必要があります。長期譲渡所得の復興特別所得税率は15%×2.1%=0.315%、短期譲渡所得の税率は30%×2.1%=0.63%となります。
上記のように、空き家を所有していた期間が5年以下だと税率が高くなります。
例えば、15年前に被相続人が購入した不動産を相続し、5,000万円で売却(取得費2,500万円、譲渡費用200万円)した場合の納税額は以下のように計算できます。
課税される譲渡所得=5,000万円-(2,500万円+200万円)=2,300万円
上記で算出した譲渡所得2,300万円に、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税率の合計20.315%を掛けると税額は以下のように計算できます。
納税額=2,300万円×20.315%=467.2万円
また、上記のケースで相続空き家の3,000万円特別控除が適用できた場合、譲渡所(2,300万円)から3,000万円を引くとマイナスとなるため、税金はかかりません。
④確定申告書類に記入する
必要な書類を準備し、適用できる特別控除などを確認したら、確定申告書や譲渡所得の内訳書に記入します。
売買契約書や領収書、源泉徴収票等に記載されている金額や不動産情報をミスなく記入していきましょう。
国税庁の確定申告用ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書や内訳書を作成すると、税額などが自動計算されるので便利です。
⑤税務署へ申告書類を提出する
不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に、確定申告書類を最寄りの申告会場へ持参、税務署に郵送、またはインターネットで書類を送信できるe-Taxで提出します。
期間中の申告会場は混雑していることも多いため、e-Taxで自宅から申告するとスムーズに手続きできます。
e-Taxでの相続不動産売却の確定申告のやり方
確定申告書等作成コーナーで作成した申告書データは、そのままオンラインで送付して手続きを完了できます。
令和5年度の所得税申告では約7割の人がe-Taxを利用しています。
e-Taxでの相続不動産売却の確定申告の手順は以下の通りです。
①e-Taxを利用するために必要なものを揃える
- マイナンバーカード(ない場合は、住んでいる自治体に交付申請が必要)
- ICカードリーダライタまたはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン
- 利用者識別番号(半角16桁の番号)⇒e-Taxのホームページから取得
②必要書類を揃える
前章で解説した売買契約書や領収書などの必要書類を準備します。
③「確定申告書作成コーナー」でデータを作成・提出
国税庁の「確定申告書作成コーナー」にアクセスし、確定申告書のデータを作成し、オンラインで税務署に提出します。
相続不動産売却時の確定申告における注意点

相続した土地や家を売って、確定申告する際に知っておきたい注意点をまとめます。
特例を活用したい場合は相続後早めに売却を依頼する
譲渡所得税を節税できる「空き家特例」は相続から3年以内、「相続税の取得費加算の特例」は相続開始から3年10か月以内に売却することが要件の1つになっています。
特例を活用したい場合は、期限内に手続きできるように、相続が発生したら不動産会社に早めに売却を依頼しましょう。
特例を適用できる条件を満たしているか分からない場合も、不動産会社に相談すれば判断してもらえます。
特別控除を利用して税額がゼロになる場合も確定申告は必要
相続空き家の3,000万円特別控除などの特例が適用できる条件を満たしていて、税額がゼロになる場合でも、必ず確定申告の手続きは必要です。
確定申告をしないと特例が適用されないため「税金が発生しているのに納税していない」状態になり、次に解説する延滞税などのペナルティを受ける可能性があります。
期限内に確定申告しないと延滞税などのペナルティが発生する
確定申告の期限は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までです。
期限内に手続きしないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があります。
無申告加算税
無申告加算税は、確定申告をしなかったり、期限後に申告したりした場合にかかる税金です。
無申告加算税の税率は申告時の状況や税額によって変わります。
- 税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合…納付する税金×5%
- 税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合…
納付する税金が50万円までの部分は10%、50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25% - 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合…納付する税金×15%
納付する税金が50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%
(参考)国税庁ホームページ|No.2024 確定申告を忘れたとき
延滞税
延滞税は、各種税金の納付期限を過ぎた場合にかかる税金です。
- 納付期限翌日から2か月以内…納付する税金×7.3%/年
- 納付期限翌日から2か月以降…納付する税金×14.6%/年
上記のように、延滞した期間が長いほど無申告加算税や延滞税も高くなるため、必ず期限内に納税を済ませましょう。
損失が出た場合は他の所得と相殺して節税できる場合がある
相続した不動産を売却した結果、損失(譲渡損失)が出た場合は、確定申告は不要です。
ただし、譲渡損失を他の不動産所得と相殺して損益通算できる「譲渡損失の繰越控除」を利用する場合は、確定申告が必要になります。
(参考)国税庁ホームページ|No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
譲渡損失の繰越控除は以下のような事例で適用できます。
- ①相続した土地や家を売却して100万円の損失が出た
- ②同じ年に他の不動産を売却して課税対象の譲渡所得が1,000万円ある
上記の場合は、①の損失分の100万円を②の1,000万円から控除して、②の譲渡所得税を節税できます。
相続した土地や家を売却して損失が出て、なおかつ他に不動産を売って出た利益がある場合は、上記の控除を適用して節税できる可能性がありますので、適用できるかを忘れずに確認しましょう。
まとめ
相続した土地や家を売って利益が出た場合は、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をし、課税所得に応じた税金(譲渡所得税)を納める必要があります。
譲渡所得税は、要件を満たしていれば、課税所得から最大3000万円を控除できる「空き家特例」や、相続税の一部を売却物件の取得費に加算できる特例などを適用して節税することもできます。
インターネットを通じて自宅で確定申告手続きを完結できる「e-Tax」は、紙の書類への記入や申告会場へ出向く必要がないため大幅に手間を省けます。
特別控除などの特例を利用するためには相続後一定期間内に売却する必要があります。不動産の相続を控えている場合は、信頼できる不動産会社へ、適用できる特例や売却方法について早めに相談することをおすすめします。
未来の財託では、相続した土地や家について、提携税理士と共に、相続税の試算からスムーズな売却までトータルでサポートいたします。相続した空き家や土地の売却でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


 0120-210-341
0120-210-341
